青森県にある日本酒を製造する会社(蔵元)は16社があり、11市町で17の酒蔵(醸造所)が稼働中です。
このページでは、都道府県別の青森県版、「蔵元一覧・酒蔵リスト」「酒蔵の特徴や傾向」を紹介します。また、蔵見学の可不可と直売所の有無も掲載、旅行や酒蔵巡りのお役に立てていただければ幸いです。
※本ページの内容は、公開および更新の時点における、当サイトが把握している範囲内の情報です。ご了承ください
青森県の蔵元一覧・酒蔵リスト
| 蔵元名・酒蔵名 | 代表銘柄 | 所在地 | 蔵見学 | 直売所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | (株)西田酒造店 | 田酒 | 青森市 | 不可 | 無 |
| ② | 六花酒造(株) | 杜來 | 弘前市 | 可(要予約) | 有 |
| ③ | 三浦酒造(株) | 豊盃 | 弘前市 | 不可 | 有 |
| ④ | (株)カネタ玉田酒造店 | 華一風 | 弘前市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑤ | (株)松緑酒造 | 六根 | 弘前市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑥ | 白神酒造(株) | 白神 | 弘前市 | 可(要予約) | 無 |
| ⑦ | (株)中村亀吉 | 玉垂 | 黒石市 | 不可 | 有 |
| ⑧ | (株)鳴海醸造店 | 菊乃井 | 黒石市 | 不可 | 有 |
| ⑨ | (株)竹浪酒造店 | 岩木正宗 | つがる市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑩ | 尾崎酒造(株) | 安東水軍 | 鰺ヶ沢町 | 可(要予約) | 有 |
| ⑪ | 八戸酒造(株) | 陸奥八仙 | 八戸市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑫ | 八戸酒類(株)・八鶴工場 | 八鶴 | 八戸市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑬ | 八戸酒類(株)・五戸工場 | 如空 | 五戸町 | 不可 | 無 |
| ⑭ | 鳩正宗(株) | 鳩正宗 | 十和田市 | 可(要予約) | 無 |
| ⑮ | (株)盛田庄兵衛 | 駒泉 | 七戸町 | 可(要予約) | 無 |
| ⑯ | 桃川(株) | 桃川 | おいらせ町 | 可(要予約) | 有 |
| ⑰ | (有)関乃井酒造 | 関乃井 | むつ市 | 不可 | 有 |
※番号はランキングや順位などを表すものではありません。
①株式会社西田酒造店
代表銘柄「田酒(でんしゅ)」を醸す、株式会社西田酒造店(にしだしゅぞうてん)は、青森県青森市にある蔵元です。創業は1878年(明治11年)。
田酒は「日本酒の原点に帰り、風格ある本物の酒を造りたい」という理念のもと、完全な手づくりにこだわり抜かれる地酒。直売所はなく、蔵の近所の特約店でのみ扱っているため、入手困難な銘柄もあります。
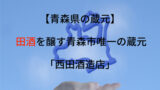
②六花酒造株式会社
代表銘柄「杜來(とらい)」を醸す、六花酒造(ろっかしゅぞう)株式会社は、青森県弘前市に蔵を構える蔵元です。創業は1972年(昭和47年)。
六花酒造が大切にしているのは「じょっぱり精神」。じょっぱりとは津軽弁で「頑固者」。頑固なまでに納得いく酒造りが続けられています。直売所が有り、蔵見学は直売所モニターから可能です。
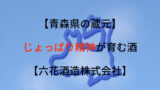
③三浦酒造株式会社
代表銘柄「豊盃(ほうはい)」を醸す三浦酒造(みうらしゅぞう)株式会社は、青森県弘前市に蔵を構える蔵元です。創業は1930年(昭和5年)。
三浦酒造は兄弟で切り盛りする小さな蔵。青森の酒米「豊盃米(ほうはいまい)」を全国で唯一使用する蔵として代表銘柄「豊盃」を醸しています。蔵見学はできませんが、直売所で各銘柄の購入が可能です。
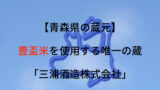
④株式会社カネタ玉田酒造店
代表銘柄「華一風(はないっぷう)」「津軽じょんがら」「斬(ざん)」を醸す、株式会社カネタ玉田酒造店は、青森県弘前市に蔵を構える蔵元です。創業は1685年(貞享2年)、創業者は玉田善兵衛。
約340年もの歴史ある老舗蔵元。現在は10代目が当代として活躍しています。見学は事前予約が必要です。直売所は利用できます。
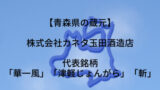
⑤株式会社松緑酒造
代表銘柄「六根(ろっこん)」を醸す株式会社松緑酒造(まつみどりしゅぞう)は、青森県弘前市に蔵を構える蔵元です。創業は1904年(明治37年)。
松緑酒造は蔵見学をうけつけていませんが、直売所は2024年に新設されてカフェスペースも併設されてるので、ゆっくりとショッピングを楽しめます。

⑥白神酒造株式会社
代表銘柄「白神(しらかみ)」を醸す、白神酒造(しらかみしゅぞう)株式会社は、青森県弘前市に酒蔵を構える蔵元です。創業年は不明(1900年にはすでに存在していたという記録は残っている)。
少量生産で質にこだわった酒造りを続ける白神酒造。地元でしか味わえない希少性の高い地酒を醸す蔵元です。
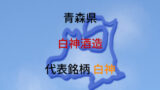
⑦株式会社中村亀吉
代表銘柄「玉垂(たまだれ)」を醸す株式会社 中村亀吉(なかむらかめきち)は、青森県黒石市に蔵を構える蔵元です。創業は1913年(大正2年)、創業者の初代中村亀吉。
日本の道100選にも選ばれた青森県黒岩市中町の通り「こみせ通り」に位置する酒蔵。蔵は1986年放送の三田佳子さん主演のNHK大河ドラマ「いのち」の撮影に使用されています。
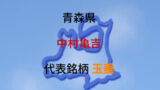
⑧株式会社 鳴海醸造店
代表銘柄「菊乃井(きくのい)」を醸す株式会社 鳴海醸造店(なるみじょうぞうてん)は、青森県黒石市に蔵を構える蔵元です。創業は1806年(文化3年)、創業者は初代鳴海文四郎。
黒石の地で200年以上もの歴史がある老舗。蔵人それぞれが互いを思いやって心を合わせ「心で醸す」ことを理念としています。
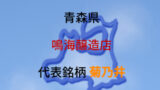
⑨株式会社竹浪酒造店
代表銘柄「岩木正宗(いわきまさむね)」を醸す株式会社 竹浪酒造店(たけなみしゅぞうてん)は、青森県つがる市に蔵を構える蔵元です。創業は1645年(天保2年)。
竹浪酒造店は江戸時代の初期に創業した、青森県内で最古の蔵元。酒造りのこだわりは「燗酒に合ったまろやかな味わいに仕上げる」ことです。蔵には直売所が併設されています。

⑩尾崎酒造株式会社
代表銘柄「安東水軍(あんどうすいぐん)」を醸す尾崎酒造(おざきしゅぞう)株式会社 は、青森県西津軽郡鰺ヶ沢に蔵を構える蔵元です。創業は1860年(万延元年)。
青森県最年少の杜氏が醸す地酒は、伝統とモダンの融合。「日本酒に馴染みのない人たちが日本酒に興味をもち楽しめるような酒造りをする」という理念のもとに酒造りが続けられています。

⑪八戸酒造株式会社
代表銘柄「陸奥八仙(むつはっせん)」を醸す八戸酒造(はちのへしゅぞう)株式会社 は、青森県八戸市に蔵を構える蔵元です。創業は1775年(安永4年)、創業者は初代駒井庄三郎。
当代(8代目)の長男が販売・営業を担当、杜氏を務めているのは次男。現代の日本酒トレンドを捉え、新たな試みを積極的に行った結果、出荷量を大きく伸ばすことに成功。海外からも高い評価を受けています。

⑫八戸酒類株式会社 ・八鶴工場
代表銘柄「八鶴(はちつる)を醸す八戸酒類(はちのへしゅるい)株式会社 ・八鶴工場は、青森県八戸市にある酒蔵です。創業は1786年(天明6年)。
八鶴工場は八戸酒類の本社に隣接する酒蔵。蔵は見学が可能で、直売所も併設されています。

⑬八戸酒類株式会社 ・五戸工場
代表銘柄「如空(じょくう)を醸す八戸酒類(はちのへしゅるい)株式会社 ・五戸工場(ごのへこうじょう)は、青森県三戸郡五戸町にある酒蔵です。

⑭鳩正宗株式会社
代表銘柄「鳩正宗(はとはさむね)」を醸す鳩正宗(はとまさむね)株式会社 は、青森県十和田市に蔵を構える蔵元です。創業は1899年(明治32年)。
鳩正宗の名は、蔵の神棚に棲みついた白鳩にちなんで付けられました。今でも蔵の守神「鳩神様」として祀られています。
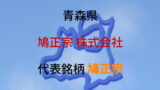
⑮株式会社盛田庄兵衛
代表銘柄「駒泉(こまいずみ)」を醸す、株式会社 盛田庄兵衛(もりたしょうべえ)は、青森県上北郡七戸町に蔵を構える蔵元です。創業は1777年(安永6年)、創業者は初代盛田平次兵衛。
酒造りのモットーは「基本に徹すること」。青森県の水と光で育った米を使うことにこだわり、「まっしぐら」をはじめ、青森県産酒造好適米「華想い」「華吹雪」「華さやか」「吟烏帽子」などを中心に使用。
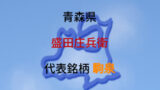
⑯桃川株式会社
代表銘柄「桃川(ももかわ)」を醸す桃川株式会社は、青森県上北郡おいらせ町に蔵を構える蔵元です。創業は1889年(明治22年)、創業者は村井幸七郎。
桃川といえば、「桃川の大杉玉」が有名。杉玉という銘柄が日本一になれますように、という願いを込めています。

⑰有限会社関乃井酒造
代表銘柄「関乃井(せきのい)」を醸す「有限会社関乃井酒造(せきのいしゅぞう)」は、青森県むつ市に蔵を構える蔵元です。創業は1891年(明治24年)。
関乃井酒造は本州最北端、下北半島唯一の蔵元。むつ湾・津軽海峡・太平洋に囲まれた下北半島の恵まれた食材に合った酒造りが続けられています。
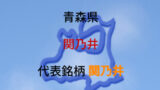
青森県の酒蔵の特徴や傾向

青森県における日本酒の酒蔵数を多い順に市町別でランキングすると、以下のようになります。
1位 弘前市:5場
2位 黒石市・八戸市:2場
3位 青森市・つがる市・鰺ヶ沢町・五戸町・十和田市・七戸市・おいらせ町・むつ市:1場
もっとも酒蔵が多いのは弘前市。弘前市は白神山地からの伏流水や岩木川水系の清らかで豊富な水源に恵まれ、古くから酒造りが盛んでした。また、弘前市が所在する津軽平野は米どころとしても知られ、華吹雪や華想いなど、地元青森の酒造好適米の栽培も盛んな地域です。津軽平野には、2位の黒石市や、つがる市なども所在しています。
八戸エリアも日本酒造りが盛んです。八戸市に隣接する「おいらせ町」「五戸町」も合わせると、エリア内には酒蔵が4場となります。
津軽杜氏・南部杜氏の伝統的な酒造りを大切にする青森県。近年は伝統を大切にしつつトレンドを意識した酒造りをする酒蔵も増加傾向にあります。若い世代や女性など日本酒に馴染みのない層のニーズをとらえた地酒は、新たなファンを開拓することでしょう。
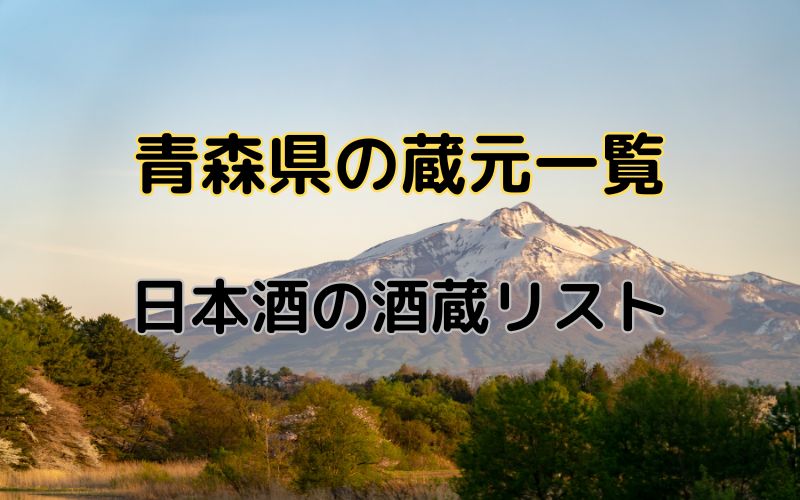



コメント