宮城県にある日本酒を製造する会社(蔵元)は29社あり、17市町で31の酒蔵(醸造所)が稼働中です。
このページでは、都道府県別の宮城県版、「蔵元一覧・酒蔵リスト」を紹介します。また、蔵見学と直売所情報も掲載しているので、旅行や酒蔵巡りの参考にしていただければ幸いです。
- 宮城県の蔵元一覧・酒蔵リスト
- ①仙台伊澤家 勝山酒造株式会社
- ②合資会社森民総本家
- ③合資会社内ヶ崎酒造店
- ④大和蔵酒造株式会社
- ⑤有限会社佐々木酒造店
- ⑥株式会社相傳商店
- ⑦阿部勘酒造株式会社
- ⑧株式会社佐浦・本社蔵
- ⑨株式会社平孝酒造
- ⑩墨廼江酒造株式会社
- ⑪株式会社佐浦・矢本蔵
- ⑫株式会社男山本店
- ⑬株式会社角星
- ⑭株式会社一ノ蔵
- ⑮株式会社浅勘酒造店
- ⑯合名会社寒梅酒造
- ⑰ 森民酒造店
- ⑱株式会社田中酒造
- ⑲株式会社山和酒造店
- ⑳株式会社中勇酒造店
- ㉑合名会社川敬商店
- ㉒萩野酒造株式会社
- ㉓千田酒造株式会社
- ㉔株式会社一ノ蔵・金龍蔵
- ㉕金の井酒造株式会社
- ㉖門傳醸造株式会社
- ㉗はさまや酒造店
- ㉘石越醸造株式会社
- ㉙蔵王酒造株式会社
- ㉚有限会社大沼酒造店
- ㉛株式会社新澤醸造店
- 宮城県の酒蔵の特徴や傾向
宮城県の蔵元一覧・酒蔵リスト
蔵元名・酒蔵名は、当サイト内の紹介ページにリンクしています。
| 蔵元名・酒蔵名 | 代表銘柄 | 所在地 | 蔵見学 | 直売所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 仙台伊澤家 勝山酒造(株) | 勝山 | 仙台市 | 不可 | 無 |
| ② | (資)森民総本家 | 森民 | 仙台市 | 可(要予約) | 有 |
| ③ | (資)内ヶ崎酒造店 | 鳳陽 | 富谷市 | 可(要予約) | 有 |
| ④ | 大和蔵酒造(株) | 雪の松島 | 大和町 | 可(要予約) | 無 |
| ⑤ | (有)佐々木酒造店 | 宝船浪の音 | 名取市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑥ | (株)相傳商店 | 名取駒 | 岩沼市 | 不可 | 有 |
| ⑦ | 阿部勘酒造(株) | 阿部勘 | 塩竈市 | 不可 | 有 |
| ⑧ | (株)佐浦・本社蔵 | 浦霞 | 塩竈市 | 休止中 | 有 |
| ⑨ | (株)平孝酒造 | 日高見 | 石巻市 | 不可 | 無 |
| ⑩ | 墨廼江酒造(株) | 墨廼江 | 石巻市 | 不可 | 有 |
| ⑪ | (株)佐浦・矢本蔵 | 浦霞 | 東松島市 | 不可 | 無 |
| ⑫ | (株)男山本店 | 蒼天伝 | 気仙沼市 | 可(要予約) | 無 |
| ⑬ | (株)角星 | 金紋両國 | 気仙沼市 | 不可 | 有 |
| ⑭ | (株)一ノ蔵・本社蔵 | 一ノ蔵 | 大崎市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑮ | (株)浅勘酒造店 | 酔舞 | 大崎市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑯ | (名)寒梅酒造 | 宮寒梅 | 大崎市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑰ | 森民酒造店 | もりいずみ | 大崎市 | 可(要予約) | 有 |
| ⑱ | (株)田中酒造店 | 真鶴 | 加美町 | 可(要予約) | 有 |
| ⑲ | (株)山和酒造店 | わしが國 | 加美町 | 不可 | 有 |
| ⑳ | (株)中勇酒造店 | 天下夢幻 | 加美町 | 可(要予約) | 有 |
| ㉑ | (名)川敬酒造 | 黄金澤 | 加美町 | 不可 | 無 |
| ㉒ | 萩野酒造(株) | 萩の鶴 | 栗原市 | 不可 | 有 |
| ㉓ | 千田酒造(株) | 栗駒山 | 栗原市 | 不可 | 有 |
| ㉔ | (株)一ノ蔵・金龍蔵 | 祥雲金龍 | 栗原市 | 不可 | 有 |
| ㉕ | 金の井酒造(株) | 綿屋 | 栗原市 | 不可 | 無 |
| ㉖ | 門傳醸造(株) | 門傳 | 栗原市 | 不可 | 有 |
| ㉗ | はさまや酒造店 | 阿佐緒 | 栗原市 | 可(要予約) | 有 |
| ㉘ | 石越醸造(株) | 澤乃泉 | 登米市 | 可(要予約) | 有 |
| ㉙ | 蔵王酒造(株) | 蔵王 | 白石市 | 可(要予約) | 有 |
| ㉚ | (有)大沼酒造店 | 乾坤一 | 村田市 | 不可 | 有 |
| ㉛ | (株)新澤醸造店 | 伯楽星 | 川崎町 | 不可 | 無 |
※番号はランキングや順位などを表すものではありません
①仙台伊澤家 勝山酒造株式会社
代表銘柄「勝山(かつやま)」を醸す、仙台伊澤家 勝山酒造(せんだいいさわけ かつやましゅぞう)株式会社は、宮城県仙台市に蔵を構える蔵元です。創業は1688年(元禄元年)。
仙台伊澤家 勝山酒造は、宮城県に現存する唯一の伊達家御用蔵という歴史ある蔵元。酒造りでは、100%特定名称酒にこだわっています。
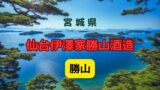
②合資会社森民総本家
代表銘柄「森民(もりたみ)」を醸す、合資会社森民総本家(もりたみそうほんけ)は、宮城県仙台市に蔵を構える蔵元です。創業は1849年(嘉永2年)、創業者は森民蔵。
2022年、創業以来はじめて酒蔵の大改修を実施。新銘柄「森民」誕生しました。
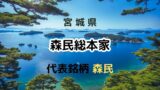
③合資会社内ヶ崎酒造店
代表銘柄「鳳陽(ほうよう)」を醸す、合資会社 内ヶ崎酒造店 (うちがさきしゅぞうてん)は、宮城県富谷市に蔵を構える蔵元です。創業は1661年(寛文元年)、創業者は内ヶ崎作右衛門。
内ヶ崎酒造店は、伊達政宗公より富谷に宿場を設けることを命じられ、富谷のまちづくりに深く関わった由緒ある造り酒屋です。

④大和蔵酒造株式会社
代表銘柄「雪の松島(ゆきのまつしま)」を醸す、大和蔵酒造(たいわぐらしゅぞう)株式会社は、宮城県黒川郡大和町に蔵を構える蔵元です。創業は1996年(平成8年)。
大和蔵酒造のこだわりは、先進の技術と手づくりの技を融合させた酒造りです。

⑤有限会社佐々木酒造店
代表銘柄「宝船浪の音(ほうせんなみのおと)」を醸す、有限会社 佐々木酒造店(ささきしゅぞうてん)は、宮城県名取市に蔵を構える蔵元です。創業は1871年(明治4年)、創業者は佐々木新助。
2011年の東日本大震災で蔵が全壊したなか、2本のタンクが破損なく残ります。奇跡的に残ったタンクの酒は、震災復興酒「閖(ゆり)」と名付けられ販売されました。

⑥株式会社相傳商店
代表銘柄「名取駒(なとりこま)」を醸す、株式会社 相傳商店(あいでんしょうてん)は、宮城県岩沼市に蔵を構える蔵元です。創業は1821年(文政4年)、創業者は相原傳兵衛。
相傳商店は奈良漬の名店として有名。日本酒づくりの副産物の酒粕を利用して、野菜を漬け込んだ奈良漬けを製造。1953年(昭和28年)には全国最初の農林大臣賞を受賞し、その品質と味わいが広く認められています。
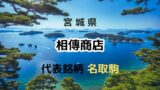
⑦阿部勘酒造株式会社
代表銘柄「阿部勘(あべかん)」を醸す、阿部勘酒造(あべかんしゅぞう)株式会社は、宮城県塩竈市に蔵を構える蔵元です。創業は1716年(享保元年)。
伊達藩の命により鹽竈神社への御神酒御用酒屋として酒造りをはじめた阿部勘酒造。高品質少量生産にこだわり、塩釜の海の幸をより引き立てる日本酒づくりが続けられています。
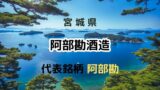
⑧株式会社佐浦・本社蔵
代表銘柄「浦霞(うらかすみ)」を醸す、株式会社 佐浦(さうら)・本社蔵は、宮城県塩竈市にある酒蔵です。佐浦の創業は1724年(享保9年)。
佐浦は、吟醸造りの名人と称される南部杜氏「平野佐五郎」の精神を受け継ぐ蔵。佐浦には平野佐五郎の「試行錯誤を恐れず、常により良いものを追求する」という「探究心の精神」が受け継がれています。
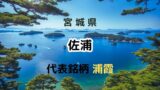
⑨株式会社平孝酒造
代表銘柄「日高見(ひたかみ)」を醸す、株式会社平孝酒造(ひらこうしゅぞう)は、宮城県石巻市に蔵を構える蔵元です。創業は1861年(文久元年)。
岩手の老舗蔵元の菊の司酒造から分家し、石巻で造り酒屋を創業したのが始まり。「魚でやるなら日髙見だっちゃ!」をテーマに、地元石巻の美味を引き立てる地酒造りにこだわる地酒づくりが続けられています。
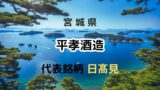
⑩墨廼江酒造株式会社
代表銘柄「墨廼江(すみのえ)」を醸す、墨廼江酒造(すみのえしゅぞう)株式会社は、宮城県石巻市に蔵を構える蔵元です。創業は1845年(弘化2年)、創業者は澤口清治郎。
墨廼江酒造が目指すは、綺麗でやわらかく気品漂う風味豊かな日本酒を醸す。少量生産による高品質な地酒造りにこだわっています。
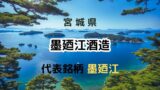
⑪株式会社佐浦・矢本蔵
代表銘柄「浦霞」を醸す、株式会社 佐浦・矢本蔵 は、宮城県東松島市にある酒蔵です。開業は1994年(平成6年)。
高品質の酒を安定供給するるために建設された、佐浦第2の蔵。
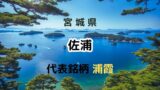
⑫株式会社男山本店
代表銘柄「蒼天伝(そうてんでん)」を醸す、株式会社 男山本店(おとこやまほんてん)は、宮城県気仙沼市に蔵を構える蔵元です。創業は1912年(明治45年・大正元年)。
宮城県初の酒造好適米「蔵の華」の誕生に注力した菅原昭彦氏が社長を務める男山本店。こだわりは、地元気仙沼で栽培される原料米での酒造り。

⑬株式会社角星
代表銘柄「金紋両國(きんもんりょうごく)」を醸す、株式会社 角星(かくぼし)は、宮城県気仙沼市魚町に本社(店舗)、同市上東側根に蔵を構える蔵元です。創業は1906年(明治39年)。
角星の「白山製造場」は、廃校となった旧白山小学校の校舎を全面改装した酒蔵。酒蔵に直売所はありませんが、気仙沼市魚町にある国の登録有形文化財に登録されている店舗があります。

⑭株式会社一ノ蔵
代表銘柄「一ノ蔵(いちのくら)」を醸す、株式会社 一ノ蔵(いちのくら)・本社蔵は、宮城県大崎市にある酒蔵です。創業は1973年(昭和48年)。
一ノ蔵といえば、あえて審査を受けず上質な清酒を二級酒として提供した「一ノ蔵 無鑑査本醸造辛口(むかんさほんじょうぞうからくち)」。一ノ蔵は、消費者が満足できる「良質な商品を正直に手を掛けてつくり続けること」にこだわり続けています。

⑮株式会社浅勘酒造店
代表銘柄「酔舞(よいまい)」を醸す、株式会社 浅勘酒造店(あさかんしゅぞうてん)は、宮城県大崎市に蔵を構える蔵元です。創業は1919年(大正8年)。
2002年(平成14年)、創業家の都合により、醸造機器を製造販売する有限会社塚本鑛吉商店に事業を継承。醸造機器メーカーのノウハウによる、人体に影響がある不純物が99%取り除かれた「純水(ピュアウォーター)」を使用した酒造りが特徴。
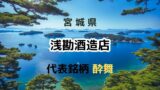
⑯合名会社寒梅酒造
代表銘柄「宮寒梅(みやかんばい)」を醸す、合名会社 寒梅酒造(かんばいしゅぞう)は、宮城県大崎市に蔵を構える蔵元です。創業は1918年(大正7年)。
寒梅酒造は、米づくりから酒造りを一貫して行う宮城県唯一の栽培醸造蔵です。2011年の東日本大震災により蔵が全壊してしまいますが、同年の12月に蔵を復興。復興後は「後悔のない酒造り」をモットーに高品質な地酒づくりが続けられています。
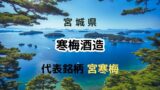
⑰ 森民酒造店
代表銘柄「もりいずみ」を醸す、森民酒造店(もりたみしゅぞうてん)は、宮城県大崎市に蔵を構える蔵元です。創業は1883年(明治16年)。
森民酒造店は4代目当主で杜氏も兼任する森民典氏が一人で酒造りをする造り酒屋です。こだわりは超軟水を使用した濃醇甘口の酒を造ること。新酒から珍しい40年ものの古酒など、さまざまな銘柄メニューがあるのも特徴です。

⑱株式会社田中酒造
代表銘柄「真鶴(まなつる)」を醸す、株式会社田中酒造店(たなかしゅぞうてん)は、宮城県加美町に蔵を構える蔵元です。創業は1789年(寛政元年)。
田中酒造店は、宮城で67年ぶりに生酛(きもと)づくりの純米酒を復活させた蔵です。生酛づくりとは、もっとも古い歴史があるとされる日本酒の伝統的な製法。田中酒造店では伝統的な酒造りを続け、「多くの人たちに日本酒文化を届けることを誇りとしていきたい」としています。
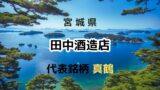
⑲株式会社山和酒造店
代表銘柄「わしが國(わしがくに)」を醸す、株式会社山和酒造店(やまわしゅぞうてん)は、宮城県加美町に蔵を構える蔵元です。創業は1896年(明治29年)。
現社長で杜氏も務める7代目当主 伊藤大祐氏の酒造りのこだわりは「Simple is best.」。基本を重視し原点を極めつつ、独自の工夫と感性を加える酒造りをモットーとしています。流通限定酒「山和」は、そんな7代目の想いが込められた銘柄です。

⑳株式会社中勇酒造店
代表銘柄「天上夢幻(てんじょうむげん)」を醸す、株式会社中勇酒造店(なかゆうしゅぞうてん)は、宮城県加美町に蔵を構える蔵元です。創業は1906年(明治39年)。
戦争の影響で一時的に酒造業を廃業し、1957年(昭和32年)に再開を果たした造り酒屋です。洋酒ブーム時代に開発された、ロックでおいしく飲める吟醸原酒が有名。

㉑合名会社川敬商店
代表銘柄「黄金澤(こがねさわ)」を醸す、合名会社 川敬商店(かわけいしょうてん)は、宮城県美里町に蔵を構える蔵元です。創業は1902年(明治35年)。
7代目当主の川名由倫(ゆり)氏は、女性杜氏としても活躍している蔵元です。創業から宮城では珍しい「生もと山廃仕込み」にこだわり続ける造り酒屋。生もと山廃仕込みの「黄金澤 山廃純米酒」は、川敬商店を象徴する一本となっています。

㉒萩野酒造株式会社
代表銘柄「萩の鶴(はぎのつる)」を醸す、萩野酒造(はぎのしゅぞう)株式会社は、宮城県栗原市に蔵を構える蔵元です。創業は1840年(天保11年)。
「自分が飲んで美味しいと思える酒」を造るのことがコンセプト。ユニークな銘柄も多く、メガネ専用や猫ラベルシリーズなどの限定酒も人気です。
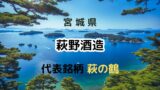
㉓千田酒造株式会社
代表銘柄「栗駒山(くりこまやま)」を醸す、千田酒造(千田しゅぞう)株式会社は、宮城県栗原市栗駒に蔵を構える蔵元です。創業1920年(大正9年)。
千田酒造が大切にしているのは地酒の命「水」。並々ならぬ水へのこだわりがあった初代は、水を求め蔵を移転。敷地内の井戸から汲まれる、名峰「栗駒山」の伏流水での地酒づくりが続けられています。

㉔株式会社一ノ蔵・金龍蔵
一ノ蔵・金龍蔵(きんりゅうくら)は、宮城県栗原市一迫にある酒蔵です。金龍蔵では「祥雲金龍(しょううんきんりゅう)」が醸造されています。

㉕金の井酒造株式会社
代表銘柄「綿屋(わたや)」を醸す、金の井酒造(かねのいしゅぞう)株式会社は、宮城県栗原市一迫に蔵を構える蔵元です。創業は1915年(大正4年)。
食事との相性を重視した「料理と仲の良い酒『食仲酒』造り」をコンセプトとする金の井酒造。米にこだわり、納得のできる酒米「阿波山田錦」と出会い、こだわりの「食仲酒」が醸されています。
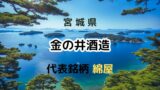
㉖門傳醸造株式会社
代表銘柄「門傳(もんでん)」を醸す、門傳醸造(もんでんじょうぞう)株式会社は、宮城県栗原市一迫に蔵を構える蔵元です。創業は1872年(明治5年)。
農業も家業とする門傳家では、ひとめぼれ・ササニシキといった食米100%の日本酒づくりが特徴。少量生産のため、市内にしか出回らない希少性の高い「知る人ぞ知る地酒」としても知られています。

㉗はさまや酒造店
代表銘柄「阿佐緒(あさお)」「桂泉(けいせん)」を醸す、はさまや酒造店は、宮城県栗原市高清水中町に蔵を構える蔵元です。創業は1757年(宝暦7年)。
1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震により、長らく自蔵での酒造りを休止。はさやま酒造店は、県内の造り酒屋の設備を借りて酒造りを続けていました。2002年(平成14年)、家業を引き継いだのは女性音楽家「かの香織」氏。そして2022年(令和4年)、実に43年ぶりに自蔵での酒造りの復活を果たしました。

㉘石越醸造株式会社
代表銘柄「澤乃井(さわのいずみ)」を醸す、石越醸造(いしこしじょうぞう)株式会社は、宮城県登米市石越町に蔵を構える蔵元です。創業は1920年(大正9年)。
石越醸造のある登米市は、米と水に恵まれた地域。石越醸造では地元の契約農家と協力して酒造好適米を栽培し、水は蔵の敷地内の深井戸から湧き出る地下水を使用。地元の恵まれた環境で醸される石越醸造の酒は、登米市内では独占的なシェアを誇る地酒として愛され続けています。
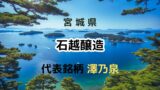
㉙蔵王酒造株式会社
代表銘柄「蔵王(ざおう)」を醸す、蔵王酒造(ざおうしゅぞう)株式会社は、宮城県白石市東小路に蔵を構える蔵元です。創業は1873年(明治6年)。
蔵人の平均年齢が若い蔵王酒造。そんな若い蔵人が中心となり考案したのが、特約店限定販売酒「Kシリーズ」。Kシリーズは通常の銘柄名「蔵王」とは異なる「ZAO」が銘柄名となっています。

㉚有限会社大沼酒造店
代表銘柄「乾坤一(けんこんいち)」を醸す、有限会社 大沼酒造店(おおぬましゅぞうてん)は、宮城県柴田郡村田町に蔵を構える蔵元です。創業は1712年(正徳2年)。
大沼酒造店は地元に根ざした造り酒屋。ブランド米を多く生産する米どころ村田町産の飯米ササニシキを使った酒造りにこだわっています。
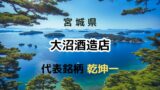
㉛株式会社新澤醸造店
代表銘柄「伯楽星(はくらくせい)」を醸す、株式会社 新澤醸造店(にいざわじょうぞうてん)は、宮城県柴田郡川崎町に蔵を構える蔵元です。創業は1873年(明治6年)。
新澤醸造店は、3年連続で世界酒蔵ランキング1位を獲得中の世界一の酒蔵。究極の食中酒「伯楽星」、高い自社精米技術により誕生した唯一無二の日本酒「零響」など、国内外から高い評価を受ける日本酒を醸す蔵元です。また、若き女性杜氏や外国人副杜氏など、年齢や性別、国籍を問わない酒造りが注目を集めています。

宮城県の酒蔵の特徴や傾向
宮城県における日本酒の酒蔵数を市町別で多い順にランキングすると、以下のようになります。
- 1位 栗原市:6場
- 2位 大崎市・加美町:4場
- 4位 仙台市・塩竈市・石巻市・気仙沼市・:2場
- 8位 富谷市・大和市・名取市・岩沼市・東松島市・登米市・白石市・村田市・川崎町:1場
酒蔵の数は、栗原町が6場でトップとなっています。栗原町は豊かな土壌を有す「米どころ」であり、栗駒山の伏流水など水資源が豊富な「水どころ」とされる地域です。こうした日本酒づくりに適した環境が、酒蔵が多い要因と考えられます。
宮城県の日本酒の特徴は、高品質な特定名称酒へのこだわりです。1986年(昭和61年)、宮城県は「みやぎ・純米酒の県宣言」。これは純米酒にこだわって酒造りを進めることを宣言したものです。現在では、県内で製造される日本酒の約9割を特定名称酒が占めています。

また、宮城県の酒蔵は女性や若い蔵人が積極的に酒造りにかかわり、活躍しているのも特徴の一つです。日本酒に馴染みの薄い若い世代や女性が、親しみをもって楽しめるようなトレンド・ニーズを意識した酒造りも期待できるでしょう。
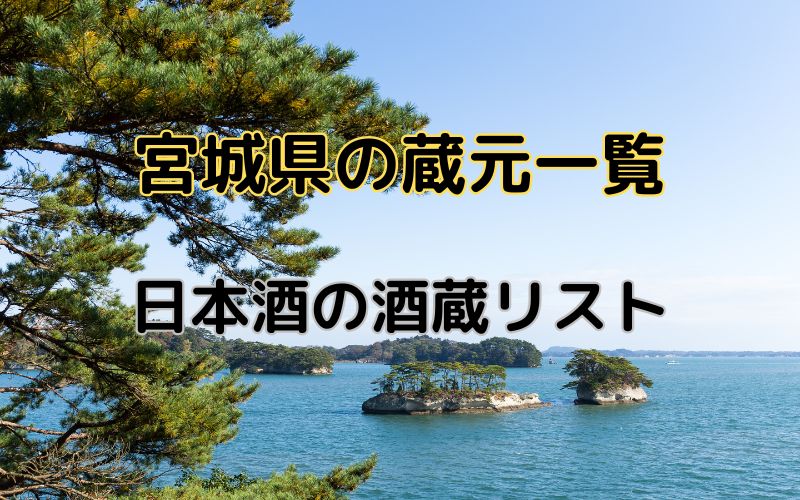



コメント