代表銘柄「國稀(くにまれ)」を醸す国稀酒造(くにまれしゅぞう)株式会社は、北海道増毛町に蔵を構える日本最北の蔵元です。
このページでは、国稀酒造の歴史やこだわり・特徴、口コミ、おすすめ銘柄、蔵の見学情報などを紹介します。
国稀酒造の歴史|明治15年に創業した日本最北の酒蔵

国稀酒造は、1882年(明治15年)に北海道増毛町(ましけちょう)で創業した、歴史ある酒蔵です。現在は、創業者のひ孫である林花織(はやしかおり)氏が4代目の代表取締役社長、夫の林眞二(はやししんじ)氏が代表取締役会長、杜氏は伊藤良介氏が務めています。
増毛町は日本海に面した北海道の北西部に位置する、農業・漁業・水産加工業が盛んな町です。江戸時代後期から昭和初期にかけ、ニシン漁を中心とした漁業で栄えた歴史があります。そういった歴史ある町で事業を始めたのが、国稀酒造の創業者「本間泰蔵(ほんまたいぞう)」でした。
新潟県佐渡出身の本間泰蔵は、1875年(明治8年)に増毛に移り住みます。そして1882年(明治15年)、呉服商や雑貨販売、海運業、ニシン漁など、手広い事業を展開する商家「丸一本間家」を立ち上げました。その事業の一つに醸造業があり、後の国稀酒造につながることになります。
醸造業を始めたきっかけは、佐渡に酒屋の知人がいるため本間泰蔵に酒造りの知識があったためです。当時、日本酒の多くは本州から入ってくるため、安いものではありませんでした。そこで酒造りの知識があった泰蔵は、増毛での自家醸造を始めたとされています。
創業から20年間は、本店の敷地内の醸造蔵で酒造りをしていました。しかし、ニシン豊による好景気が続き、酒の需要が高まったため、敷地内の醸造蔵では生産が追いつかなくなってしまいます。そこで1902年(明治35年)、地元の軟石を使用して現在地に酒蔵が新たに建設されました。
新たな蔵を構えた同年に合名会社となり、丸一本間合名会社酒造部が誕生しました。合名会社の設立から100年目の2001年(平成13年)、現在の社名である「國稀酒造株式会社」に改名し、現在に至ります。
参考
國稀酒造「KUNIMARE’S HISTORY」
地酒蔵元会「歴史背景 国稀酒造株式会社」
北海道HP「本間泰蔵」
國稀酒造のこだわり|毎日楽しめるおいしい普通酒

國稀酒造の日本酒のこだわりについて、代表取締役会長の林眞二氏はホームページで以下のように語っています。
普通酒とはかつて二級酒と呼ばれたお酒で、テーブルワインのように安価で気軽に飲めるお酒のことです。普通酒の場合、価格を抑えるために精米歩合を高くするのが一般的ですが、毎日の晩酌で楽しむお酒こそ妥協せずにおいしくしたいという想いから、國稀の普通酒は純米酒や本醸造酒と同レベルの精米歩合65%にしています。おかげさまで業界の方々から「こんなに美味しい普通酒は初めて」というありがたい言葉もいただきました。
出典:國稀酒造「KUNIMARE FEATURE」
このように、國稀酒造では晩酌などで毎日飲む酒こそ妥協せず、おいしくしたいというこだわりがあります。
特定名称の日本酒よりも一般的には安価な普通酒。国稀酒造では、精米歩合を高くしてコストを抑えるのではなく、精米歩合65%と妥協せず、おいしくて求めやすい普通酒を提供し続けています。
國稀酒造の日本酒の特徴|軟水の中でも硬度の低い水

国稀酒造では、国稀の味の基調を「穏やかな辛口」と表現しています。この特徴を生み出しているのは、仕込み水ではないでしょうか。
國稀酒造では仕込み水に、暑寒別岳(しょかんべつだけ)の伏流水を使用。この伏流水は軟水の中でも硬度が低い水です。軟水で造る日本酒は、口当たりなめらかですっきりとした味わいになる傾向があります。ただ、発酵が緩やかなため、発酵を停滞させないため高い技術とが必要です。
國稀酒造では、その難しい水を杜氏をはじめとした職人たちの知識と技術、経験により、コントーロールしています。それにより軟水の中でも特に硬度が低い暑寒別岳の伏流水で、國稀酒造の特徴である「穏やかな辛口」が生み出されているのです。
國稀酒造の酒蔵見学情報
國稀酒造の酒蔵は、見学可能です。また、ショップでお土産を選んだり試飲したりすることもできます。
- 住所:北海道増毛郡増毛町稲葉町1丁目17
- 営業時間:9:00〜17:00(見学は9:00〜16:30)
- 休業日:年末年始
- 入場料:無料
休業日は年末年始ですが、不定期休業日がある可能性もあるので、事前に確認することをおすすめします。また、10名以上の団体での見学は事前予約が必要です。
以下にマップと外観を載せているので、参考にしてください。
【国稀酒造のマップ】
【国稀酒造の外観】
蔵やショップの様子がわかる動画があったので載せておきます。
また、増毛町には國稀酒造の前身である丸一本間家の国指定重要文化財「旧本間家住宅」も残されています。國稀酒造から徒歩2分程度なので、合わせて足を運んでみてはいかがでしょうか。
国稀酒造の日本酒の口コミ・レビュー
X(旧Twitter)に寄せられている、國稀酒造の口コミ・評判・レビューなどを紹介します。國稀は、どんな人が飲んでいて、どんなシーンで楽しまれているのか、参考にしてみてください。
回鍋肉
冷凍しといた
手づくり餃子🥟日本酒
國稀器が可愛い😍
今日もらった
八朔も pic.twitter.com/xstipzPsdq— Chie🌾🥶 (@senatousanchi) March 12, 2025
東藻琴のチーズと、増毛國稀の日本酒で華金スタート‼️
そして、今夜のMリーグは見応えあるぞ❗ pic.twitter.com/uN7zvQk15x— リゼルヴァ (@fe776riserva) January 31, 2025
宗谷産生たこの陶板焼うめえ
日本酒は國稀 pic.twitter.com/7Yr5A6hnBm— kinjo (@kokesi_360) January 18, 2025
国稀は食事のシーンに選ばれている口コミが多いようです。中華、刺し身、チーズなど、さまざまな料理と合わせて楽しまれています。宗谷産生たこの陶板焼など、北海道産の食材を使った料理との相性も抜群のようです。こうした酒と料理の口コミは、日本酒選びの参考になります。
増毛の地酒 國稀酒造のおすすめ銘柄4選
北海道増毛町に蔵を構える日本最北の造り酒屋「国稀酒造」のおすすめは、以下の4銘柄です。
- 國稀 佳撰
- 國稀 特別純米酒
- 國稀 大吟醸
- 北海道限定 純米吟醸 國稀
北海道限定 純米吟醸 國稀のレビュー記事もあるので、合わせてご覧になってみてください。

国稀 佳撰
国稀 佳撰は「毎日楽しめるおいしい普通酒」という、国稀酒造こだわりの普通酒です。まろやかですっきりな芳醇な味わいが楽しめます。
| 原材料 | 米・米麹(国産)・醸造アルコール |
|---|---|
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール度数 | 15.5度 |
| 甘辛 | 中口 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜熱燗 |
精米歩合65%と妥協のない普通酒を、ぜひお楽しみください。
國稀 特別純米酒
| 原料米 | 五百万石 |
|---|---|
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール度数 | 15.5度 |
| 甘辛 | やや辛口 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜ぬる燗 |
國稀 特別純米酒は、ふくよかな香りと軽快な味わいが楽しめる一本。純米酒でありながら、すっきりとした飲み口をお試しください。
國稀 大吟醸
國稀 大吟醸は、山田錦を38%まで丁寧に磨き上げた、高品質の大吟醸酒です。
| 原料米 | 山田錦100% |
|---|---|
| 精米歩合 | 38% |
| アルコール度数 | 15.5度 |
| 甘辛 | 中口 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜冷や(常温) |
華やかな香りと軽快な味わいが楽しめる大吟醸酒。自分で楽しんでも良し、プレゼントや贈り物、お土産としても喜ばれる一本です。
北海道限定 純米吟醸 國稀
北海道限定 純米吟醸 國稀は、北海道産酒造好適米「吟風」を使用した純米吟醸酒です。
| 原料米 | 吟風 |
|---|---|
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度 | 15.5度 |
| 甘辛 | やや辛口 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜冷や(常温) |
最北の酒蔵が醸す、北海道限定の一本は、北海道の地酒にふさわしい清々しい味わいが特徴です。

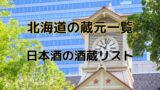



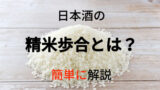





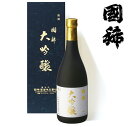


コメント